Buying Guide 購入ガイド

不動産購入の流れを8段階で解説します。資金計画から不動産の引渡し、確定申告まで、一連の手続きの注意点などを簡単にまとめました。不動産の購入をご検討中の方はご参照ください。
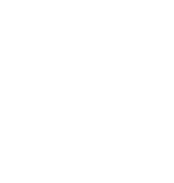
資金計画を立てる
不動産は高額な買い物ですので、早い段階で購入に必要となる費用の全体像を把握しておくことが重要です。

登録免許税も司法書士報酬も登記する内容によって異なります。(金額が高くなれば印紙代も高くなります)。
所有権移転の日を基準にして日割り清算します。
取得する不動産の金額によって仲介手数料も変動します。なお、仲介手数料の報酬基準は国土交通省が定めたものです。なお、不動産会社に依頼しても不動産売買が成立しなかった場合には仲介手数料は発生しません。
一般的には、不動産売買契約じ時点で半額、物件の引渡し時に残りの半額を支払います。
まず不動産購入の予算を算出して、その条件にあう不動産を探す方が効率的です。
購入予算を算出するには、まず毎月の住宅のローン返済にいくらまで充てられるか、自己資金としていくら用意できるか、という点を洗い出していくことになります。
購入可能な物件価格を算出するための計算式を簡単にまとめると次のようになります。
返済可能な住宅ローン借入額+(自己資金-諸費用)=購入可能な物件価格
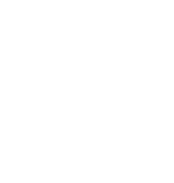
物件情報の収集
不動産にはそれぞれ個性があり、一つとして同じものはありません。
一口に物件情報といっても、金額、立地、間取り、周辺環境や利便性など、多数の要素があります。

ただし、インターネット上の情報には売主が誰なのかは書かれていないので、売主に直接アプローチすることはできません。
不動産売却は、通常、不動産会社に依頼しますので、インターネット上の物件情報には、その物件を仲介してくれる不動産会社が書かれています。
不動産の仲介手数料は、売買契約が成立して初めて発生する仕組みになっているので、物件探しを相談しても一切費用はかかりません。
やはり、不動産のことは不動産取引のプロに相談するのがもっとも近道といえます。
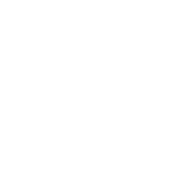
物件を見学する
物件の見学にもお金はかかりません。気になる物件が見つかったら積極的に物件を申し込んでみましょう。物件見学のポイントを簡単に解説します。

ご自分で何度か曜日や時間帯、天候などの違う日で周辺環境を確認してみることをお勧めします。
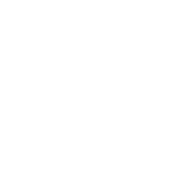
不動産売買契約の締結
重要事項の説明を受け、契約条件について買い主・売り主双方が合意したら、売買契約を締結します。

まずは購入の意思があることを売主に伝えるため、不動産購入申込書(買付申込書などと呼ぶ場合もあります)を提出するのが一般的です。
そして、購入申込書を提出してから、売買金額や売却時期などの交渉が始まるのです。もちろん、値下げなどの交渉はご自身ではなく不動産会社に依頼します。
事前審査とは、正式な申し込みの前に、返済能力などを最小限の情報から短期間で判断する審査です。実際に住宅ローンが借りられるか、契約前に簡単な審査をしておくのです。
なお、これらの調査結果は「重要事項説明書」「物件状況等報告書・設備表」としてまとめられ、契約時に買主に交付されます。
法務局では、不動産登記簿を取得して、その登記簿に記載されている事項(所有者など)を調査したり、公図や測量図などを取得して、近隣との権利関係(面積、境界)などを確認します。
たとえば、法令の規制によって、2階建て建物しか建築できないエリアや、今ある建物が古くなっても新しく建物を建築することが許されない物件などもあるのです。
こうした土地や建物に関する法令上の規制は多岐にわたるため、役所調査は慎重に行われます。
道路との接続状況や近隣との境界を調べたり、建物の状況(雨漏り、シロアリ、付属設備など)を詳細にチェックします。
重要事項説明書はページ数のボリュームも多く、使われている言葉も難しいので、分からない点があれば担当者に聞いてみましょう。
なお、重要事項説明は不動産売買契約の前に行わなければなりませんが、重要事項説明、売買契約の順で同日に行われるのが一般的です。
不動産売買契約書には、取引条件がこと細かに記載され、売主と買主双方に交付されます。
もし、契約後に契約に反する行為があった場合には、高額な違約金が発生することもあるので、不明な点があれば必ず担当者に確認してください。通常は売買契約の締結と同時に手付金を支払います。
手付金(売買金額の1割が目安)、実印、仲介手数料の半金、収入印紙代、本人確認資料(運転免許証など)
※このほか、住宅ローンを利用される場合は、ローン申込み用書類も必要となります。
ケースごとに必要書類が異なるので、あくまで参考としてお考えください。
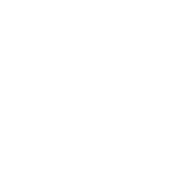
金銭消費貸借契約(住宅ローン)の締結
住宅ローンを利用する場合は、不動産売買契約後にローンの申込を行います。
住宅ローンを借りる契約のことを金銭消費貸借契約といいます(そのため、略して金消(きんしょう)と呼んだりします)。

ンバンク、ネットバンクなどがあります。このほか労働金庫やJAバンクなども住宅ローンを取り扱っています。
また、住宅金融支援機構のフラット35(民間金融期間と住宅金融支援機構が提携した長期固定型住宅ローン)を多く取り扱っているモーゲージバンクも増えてきました。
金融機関にはそれぞれに特色があり、金利や貸出条件も異なるので、自分の条件にあう住宅ローンは、不動産取引のプロである不動産会社に相談するとよいでしょう。
金融機関ごとに必要となる書類が若干異なるので、詳しくは担当者に確認してください。
・実印
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・住民票
・住民税決定通知書
・収入証明書(または所得証明書)
・不動産売買契約書
・重要事項説明書
・融資の申込書類一式
・印紙代
万一、売買契約書で定めた期限までに、金融機関から融資承認がおりなかった場合、残念ながら売買契約は解除となります。融資がおりなかったのは買主の責任ではないので、契約解除による違約金は発生しません。
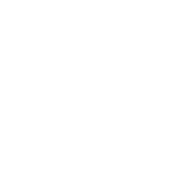
決済・引渡し
不動産売買契約は、売主が不動産を売り渡し、買主が売買代金を支払う、という契約です。
決済日には、売主、買主、司法書士などの関係者が金融機関に集まり、所有権移転登記の準備、融資の実行、売買代金の支払いが一気に行われます。

・仲介手数料の残金
・登記費用(登録免許税)
・司法書士への報酬
・固定資産税・都市計画税、管理費などの清算金
・住民票
・実印
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの、抵当権設定時のみ)
・ご本人確認資料(運転免許証など)
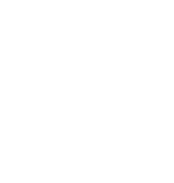
物件へのご入居準備
実際にご入居される際の、引っ越しやリフォームについてです。

このほか役所や学校などへの移転の届け出、保険など各種契約の住所変更届も忘れてはいけません。
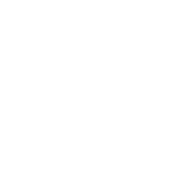
確定申告
住宅ローン控除を受けるには、初年度に必ず確定申告が必要となります。

ただし、住宅ローン控除の適用を受ける場合、サラリーマンであっても確定申告の手続きが必要です。確定申告は、物件に入居した翌年に行います。
・不動産売買契約書の写し
・新住所の住民票
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得)
・耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し(一定の築年数を超過した住宅の場合、適合証明機関から交付)
・確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
・認印
親から住宅購入資金の援助を受ける場合には、贈与税が課税されない(または軽減される)特例措置があります。特例の適用を受ける場合は、贈与を受けた翌年に確定申告の手続きが必要となります。
このほか役所や学校などへの移転の届け出、保険など各種契約の住所変更届も忘れてはいけません。